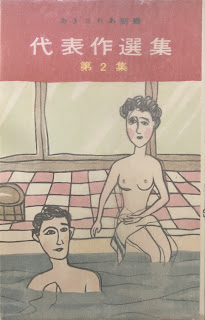フレデリック・フォーサイス『ジャッカルの日』/マイケル・バー=ゾウハー『無名戦士の神話』/トマス・ハリス『ブラック・サンデー』/ジェームズ・M・ケイン『郵便配達は二度ベルを鳴らす』/『濹東綺譚』永井荷風/アーサー・ヘイリー『ニュースキャスター』/ノーマン・メイラー『裸者と死者』/ロバート・バーナード『暗い夜の記憶』/ジョン・D・マクドナルド『死刑執行人』/中里介山『大菩薩峠』/マルセル・プルースト『失われた時を求めて』/川端康成『雪國』
これらは本書に出てくる作家・作品のほんの一部。通り一遍に褒めちぎる筈もなく、疑問や不満をためらうことなく投げ掛けるのが信彦流。シムノンなんて、敗戦後一通り読んだけれど映画化されていた『男の首』以外どこが面白いのかわからなかった、と吐露しているし、アメリカの大衆小説はやたら長くなってしまったとボヤきもする。
今日の本題はここから。本書を読んでいると個人的に押さえておきたい箇所がちょこちょこ出てくるのでメモ代りに書いておく。もちろん日本の探偵小説界に関する小林のコメントである。
◆ 谷崎終平による回想記『懐しき人々・兄潤一郎とその周辺』には、「蓼食う虫」のモデルとして高夏秀夫=佐藤春夫/阿曾=大坪砂男だと述べてあって、〝後者には驚かされた〟と小林は書いている。
◆ 本書72頁にはこんな記述が。
〝一九六〇年前後のいわゆる〈推理小説ブーム〉のころ、推理小説では直木賞がとれないというのが常識であった。当時の関係者なら誰でも知っていることだが、戦前に直木賞を得た推理作家が選考委員にいて、推理小説を片っぱしから落とした。(中略)いかになんでもズレているというわけで、問題の推理作家は選考委員から外された。〟
◆ 一つ面白い場面があれば、あとは少しぐらい出来が悪くてもよい、というのが植草甚一の推理小説感。東京創元社と仲が悪くなったあとの植草に江戸川乱歩が『別冊宝石』の作品選定を頼んだが、その好みには一般性がなかった。
◆ 209頁「松本清張の語り口」の末尾には〝はるかむかし、ぼくは、石神井の旧松本邸を訪れて、原稿を依頼したことがある。〟としか書かれていないが、後年のコラムで小林は、最初清張は原稿を書くことを了承していたのに実際受け取りに行くと「そんな約束をした覚えはない」と一蹴された内情を暴露。清張に対してはそこまで怒っていなかったようだが、木々高太郎にはかなりフンガイしている小林。
◆ 鮎川哲也の編集した光文社文庫『硝子の家』を読んで、小林は島久平「硝子の家」に対し〝なつかしい。ガラス張りの家(一九五〇年にはこんな家はあるはずがなかった)の中での密室殺人で、三百枚余の(当時の用紙事情からすれば)〈大作〉である。〟と語っている。
(銀) ブックガイド・エッセイでありつつ、こんな風に私の気を引く情報がちりばめられているのだから、小林信彦の本を時々読み返す癖はやめられない。それにしても木々高太郎の直木賞選考における言動について、探偵小説関係書籍で誰も触れようとしないのは何故なのか。小林も感情的になりやすい性格だからしっかり調査すべきとはいえ、こんな事してたんじゃ木々は当時の新人ミステリ作家だけでなく、その周辺からも悉く人望を失ってしまったんじゃないの?