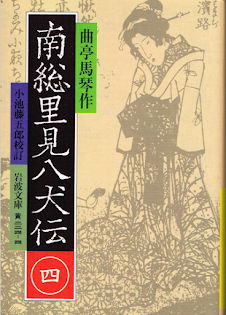NEW !
国書刊行会
2022年3月発売
★★★★ 森卓也が小林信彦を・・・
本号に鈴木義昭が寄稿している「布村建追悼」は、 『映画秘宝』があのような末路を迎えなければ本来あちらに載っていたのではないか。 鈴木は『映画秘宝』の常連ライターだったし。 この『映画論叢』は今は亡き『彷書月刊』に似たサイズで、最近の映画は扱わない方針を特に 打ち出している訳でもなかろうが、バックナンバー一覧を見ても日本の元号でいう昭和以前の 国内外映画に思い切り特化した誌面作りがされている。強いて言うなら国書刊行会の取引規模 自体が洋泉社とは違うので、入荷する書店が限られているのが難点。 『映画秘宝』のようなカラーページは無く、中身の佇まいも『彷書月刊』っぽい。
今迄『映画論叢』を読みたかったけど買うのをずっと我慢していたのは湯浅篤志による探偵小説関連映画についての記事が一冊の単行本になった時にまとめて読みたかったから。 (もっとも、氏が「そのうち単行本を出します」なんて発言しているのを確認した訳でもなく、 本当に単行本化されるかどうか定かではない) それでも今回初めて『映画論叢』を買って読んでみて、 やっぱり湯浅の記事は面白くてためになる。本号ではアルセーヌ・ルパン・シリーズの翻訳者として知られる保篠龍緒に関連した戦前映画三本について書かれており、 その対象作品はこちら(☟)。
♣ 『茶色の女』(昭和2年公開)
原作:モーリス・ルブラン 脚色:星野辰男(保篠龍緒の本名)
監督:三枝源次郎 出演:南光明ほか
♣ 『紅手袋』(昭和3年公開)
原作:保篠龍緒
脚色:大島十九郎
監督:川浪良太
出演:玉木悦子(=環歌子)ほか
♣ 『妖怪無電』(昭和4年公開)
原作:保篠龍緒
脚色:木村恵吾
監督:木村次郎
出演:美濃部進(=岡譲司)ほか
どの映画もフィルムは現存してなさそうで、鑑賞することができないのは仕方ないとはいえ 当時の活字メディアを丹念に調べて情報を拾い集めてくれているのは有難い。 湯浅の専門は探偵小説だから他の記事と並べたら氏の書くものだけ浮いてしまわないかな・・・と懸念していたが、何の遜色もなく本誌のカラーに溶け込んでいる。 どんなに時間がかかってもいいから、これら一連の記事は是非一冊の書籍にまとめてほしい。
それほど湯浅篤志の記事を読むのを我慢していたくせに、何故今回『映画論叢』を買ったのかというと、アニメーション/映画をはじめとしたエンターテイメント研究で知られる森卓也の寄稿「或る作家の横顔 尾張の幇間」が掲載されているから。 この記事というのが、長年森とは盟友だとばかり思っていた小林信彦について、 どうにも不穏な発言に満ちていて正直戸惑わざるをえない内容。 おおまかに整理すると要旨はこんな感じ。
何かの対象を評する時、自分(小林)の考えだけでは不安だから森に感想を聞き「森卓也もそういっていた」という連帯感の安心を得る為に、しょっちゅう小林から(時には乱暴な形で)意見を求められてきた過去に対する不快感
それ以外にも、森が苦々しく感じてきた小林の言動の数々
小林を否定的に見ているらしい人達(淀川長治/石上三登志/佐藤重臣/明石家さんま/ 古今亭八朝/永六輔/山藤章二)の例
私は森卓也の著作を殆ど読んだことがなく、その存在は小林信彦著書の中で確認してきただけ。一方、小林の著書はほぼ全て読んできた。だからハッキリ言えるのだけど、 老舗和菓子屋の長男として生まれた小林信彦はハンパなく気位が高い。 俗な言い方をすると、大抵の場合において〝上から目線〟。 だって臆面もなく「芸の筋がよいタレントを、うまくエスカレーターに乗せる ― それがぼくの 趣味であった。」(要するにタレントが成功できるように自分が導いてやる、という意味)と 言っちゃう人だ。世の中植木等や谷啓のような寛大なオトナばかりじゃないのだし、 こういう小林に反感を持った者はきっといただろう。でも、 我々読者がそんな小林の困った欠点も知った上で彼の本を読んできたように、森卓也もそういう小林の部分を承知の上でずっとつきあいを続けてきてるもんだとばかり思ってきたけど、 どうも今回の文章を読む限り、最近何か突発的なきっかけで怒りが爆発したんじゃなく、 以前からずっと抑えに抑えてきたものが噴出してしまった、そんな気配がする。
森の文章を読んで私の頭をよぎったのは、小林信彦という人は『ヒッチコックマガジン』の時代に変に芸能界に染まってしまったのは(稲葉明雄が心配したとおり)不幸だったかもしれないということ。そのおかげで読者はずいぶん楽しませてもらったけれど、 芸能界の人ってすべからく腹の中で「自分は一般庶民よりはるかに偉い」って思ってるからね。 小林も華やかなTV業界の一員になってしまって、知らず知らずのうちに元々持っていた高慢さがいつしかあまり好ましくない形で増長し、こういう事態を招いてしまったか。
例えばビートルズ論争。 あれも小林に『ミート・ザ・ビートルズ』の誤りを伝えたのが仮に井原高忠のような、 明らかに小林が自分より格上だと見ている人から云われたのであれば小林も大人しく聞き入れていたと思う。それがたまたま松村雄策という、小林より知名度が低い人物だったが為に、 自分よりも格下の存在だと蔑んだ結果「半狂人」なんて発言をしてしまった。 松村の指摘を受け入れるにしろ受け入れないにしろ、もっとマシな対応の仕方があった筈。 この言い方は明らかに小林のほうが悪い。格下に見ている人間に対して居丈高な態度を取る癖は 若い頃のみならず脳梗塞で倒れるまでは『文春』連載でも少なからず見受けられた。 中野翠を下に見ているのはわかっていたが、まさか森卓也にもそこまで・・・。
小林が昭和7年生まれで、森が昭和8年生まれ。 二人ともほぼ同学年といえるし、卒寿を迎える直前にある。 年齢的にこんな事でいちいちキレていては、世間体を心配するその前に健康によくない。 なんでまた森卓也が急にこんな文章を世に発表したのかさっぱりわからないけれど、 九十歳の老人の罵り合いなど見たくはない。 小林はこんな発言を森がしている事なんて知らなくていいし、 森も言いたい事は山ほどあるのだろうけど、できれば刀を鞘に収めてくれるのを願う。
(銀) 森卓也の文章を普段読んでいないから、彼の筆致というものが詳しくわからないけれど いくら怒気が混じっているとはいっても、話の論旨がややあっちこっちにフラフラしているように感じられて、それが単に高齢のせいならまだいいが、 本来の森ならもっと整然とした文章を書きそうなのに、そう見えないのが少々気にかかる。 twitter中毒になって勝手に自分でキレて、アタマがプッツン状態になってバチが当たればいい 老害野郎は世間にいくらでもいるが、森と小林にはそうなってもらいたくはない。
ちなみに「レッツゴー三匹」の表記でも別にいいんじゃないの?と思ってたら、 ネットでググると「レツゴー三匹」とばかり出てくる。 この件はやっぱし森が正しいのか・・・。