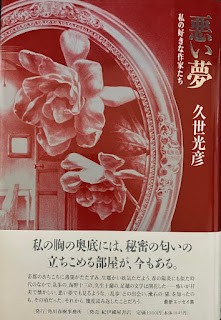読む価値があると思った下山事件の関連書籍は何冊か紹介してきたけれども、西暦2000年という大きな時代の節目を迎えたあと諸永裕司/柴田哲孝/森達也らによって上梓された比較的新しめのものには、今一つ深入りできずにいる。彼らの主張を全否定するつもりは無い。しかし、疑り深い(?)私には承服しかねるところが多いのもまた事実なのだ。
ひとつ例を挙げるとすれば亜細亜産業。柴田哲孝は自分の祖父が亜細亜産業の一員で、下山事件実行犯に加わっていた可能性もあると述懐している。この辺の情報を初めて目にした時、「なんだって今頃そんな事実が浮上してきたの?」というのが私のファースト・インプレッションだったし、「話が少々うますぎやしないか?」とも感じた。
勝浦にある亜細亜産業の缶詰工場で下山総裁は殺されたと見做す説も然り。同じ千葉県でも浦安あたりならともかく、総裁が失踪した日本橋、そして屍体発見現場である綾瀬、この都内二カ所と勝浦を比較した場合、屍体を再び都内へ運び、衆目を集めさせる計画だったとしても、実行に移すとなると距離が相当離れすぎていて、現実味に乏しい。
どこまで行っても解決の糸口は見えない。あまりに下山事件の闇が深すぎるため、いつのまにか〝下山ビジネス〟なるものが芽吹いてしまったんじゃないか・・・・そんな疑問さえ抱くようになった私には例のNHK『未解決事件 File.10 下山事件』も、それっぽい実録ドラマを見せることのみ重視しているだけのpointlessな番組でしかなかった。
そうは言いながら、ちまちまチェックしていたネット連載もある。『讀賣新聞オンライン』にて令和4年12月から翌5年9月にかけてupされた「下山事件の謎に迫る」がそれで、筆者の木田滋夫は昭和46年生まれの読売新聞記者。今回取り上げる『下山事件~封印された記憶』はそのネット連載分に加筆、更に巻末資料をプラスするなど再構成した上で、紙の本として先日発売された。
✸
本書の中で鍵となるのは、新たに出現した三つの紙資料。
第一の資料は足立区立郷土博物館の文芸員が平成18年、下山事件の文献として広島の古書店から『改造』と『中央公論』の二誌を購入した際、一緒に挟まれていた事件当時の捜査資料と思しき『ガリ版資料』だ。昭和24年12月にマスコミへリークされた『下山白書』とその『ガリ版資料』を見比べてみると、『下山白書』が自殺説寄りに結論付けられているのに対し、『ガリ版資料』のほうは疑義の問題点を箇条書きにした簡単な内容とはいえ、自殺にも他殺にも偏りの無いフラットな姿勢で綴られている。
二番目の資料は、神奈川で教師として働いていた永瀬一哉が旧知の間柄である本書の筆者・木田滋夫へ知らせてきた『下山事件捜査秘史 元東京地方検察庁検事 金沢清』という、昭和58年にタイプで打たれた八枚の文書。なんでも永瀬は自分の教え子から、「身内に下山事件を捜査した元検事がいる」と云われ、二度ほど金沢清と接見したそうだ。その時に金沢から手渡されたのが上記の『捜査秘史』だった。
これらの資料は量的に嵩張るものでもなく、本書巻末に【資料編】として全文収録されている。結果的に明言こそしていないが、木田滋夫の視線は自然と他殺説側に向いている様子。下山事件が発生した直後に『読売』と『朝日』が他殺を主張していたことを盲信して、読売の記者である木田も最初から他殺説に凝り固まっていた訳ではなかろうが、どのみち本書の立ち位置を知っておくに越したことはない。
✸
新資料はもう一つある。
平成21年、前述の足立区立郷土博物館を訪れ、紙の束をホチキス止めしただけの『小菅物語』と題された自伝的な小説を置いていった来館者がいた。文芸員からその事を聞かされた木田は、『小菅物語』を書いた82歳の老人・荒井忠三郎を運良く見つけ出す。老人の住まいは下山総裁轢断現場の近所だった。その後、木田は十五年近くも荒井とやりとりを重ね、小説における創作と実話の部分とを切り分けるべく、各種証言を引き出すことに努める。荒井は令和5年7月死去。
或る意味では、このパートが本書のハイライトかもしれない。下山事件の頃、荒井が働いていた彼の長兄が経営する町工場〝荒井工業〟は総裁轢断現場から遠くない場所にあり、矢田喜美雄の『謀殺 下山事件』に登場する不審な外車が目撃された朝日石綿工場のちょうど裏手に位置するばかりでなく、荒井工業もまた亜細亜産業の系列であることが判明。木田が荒井から得た情報は100%裏付けが取れている訳ではないと断りつつも、綾瀬方面における謎のミッシング・ピースを埋める要素を内包していたのだ。
諸永裕司/柴田哲孝/森達也らの本の内容に対して私が思ったように、木田もまた荒井の証言について「話ができすぎている」と感じ、柴田哲孝のもとへ会いに行き、荒井証言から得た推理の鑑定を乞う。木田が導き出した〝線路轢断より前に総裁が殺害されていた現場を荒井工業の敷地内と見る説〟は柴田からすれば自著にて提示した〝勝浦殺害説〟とは相反するのだし、下山事件研究者としてのプライドもあるだろうから、木田の持ちかけた話を否定するどころか、一切耳を貸さぬ態度を取ることも予想されたに違いない。
ところが『讀賣新聞オンライン』~「下山事件の謎に迫る」最終回(☜)を見てほしいのだが、柴田は勝浦説の間違いを素直に受け入れている。これは一見出来そうで、なかなか出来る事ではない。私はちょっと柴田のことを見直した。本書にて明らかにされた新たな情報を踏まえ、今後アップデートされた柴田哲孝の下山本が再び世に出るかもしれない。
✸
柴田が木田の発見を尊重したことで、本書に対する好感度もグンと上がったけれど、拭い去れぬ疑問点は依然として残っている。昭和の時代は遠くなったにもかかわらず、下山事件について何か証言しようとする人々は、核心に迫るところを訊かれた途端、どうして皆一様に口を閉ざしてしまうのだろう?あの時分社会を取り巻いていた得体の知れぬ不気味さをリアルタイムで知っている彼らからすれば、いくら時が経とうと、刷り込まれた恐怖は抜けないのかもしれない。でもそれなら、第三者に読まれることを意識した思わせぶりな自伝小説をわざわざ書いたりする必要など無い訳で・・・怖い、でも言わずにはいられない・・・それが人の性(サガ)なのか?
これまで下山事件の関連書籍上にて飛び交ってきたまことしやかな数々の説に、どれだけ我々は翻弄されたか、思い返しただけでも苦笑してしまう。
柴田哲孝は木田にこう語っている。
〝荒井証言を初めて聞いた瞬間に、私は思いました。「ああ、俺ははめられたな」と。
今思うと、あの情報提供者は、本当の「現場」から私の目をそらせようとしたのでしょうね。
下山事件では決まって、核心に迫るジャーナリストが出てくると、かく乱する情報を何者かが吹き込んでくるんです。〟
これを素直に受け取っていいものか・・・・ハッタリを吹聴するのは下山事件を追っているジャーナリスト本人なのか、それとも彼らが証言を得ようとしてアプローチする取材対象者なのか。いったい誰の言うことを信じたらいいか、もうよく分からんというのが正直な感想である。私が〝下山ビジネス〟などと揶揄したり、下山本に対して「承服しかねるところが多い」と言いたくもなる理由は、見えないところで作り話を捏造する輩がウヨウヨしている気配がそこはかとなく伝わってくるからなんだよな~。
(銀) 本書は総論めいた内容でなく、240ページ弱のハンディな単行本だし、多くを望むのは無理だと分かってはいるのだが、せっかく著者が読売の人間ゆえ、社内にアーカイブされている下山事件関係の旧い写真が多数あるだろうから、それらを惜しみなく収録してほしかった。ネット連載時よりも写真の数が減っているのは大変残念。
■ 下山事件 関連記事 ■