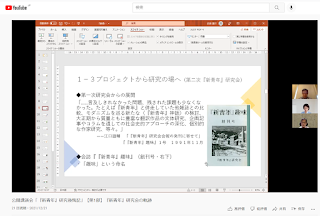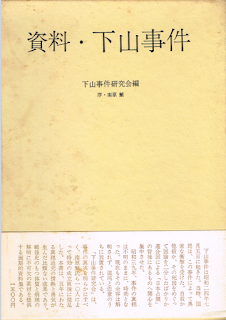♣ 当Blog 令和3年(2021年)7月19日にて、昭和24年7月に日本中を震撼せしめた未解決事件「国鉄総裁下山定則氏の失踪と轢死の謎」を知るにあたり読んでおくべき書籍はどれなのか言及したが、もう少し補足しておきたいなと思ったので今回はこの『資料・下山事件』を用いてフォローしていきたい。書名のとおり、本書は下山事件に関する重要なデータや当時の関係者証言のアーカイヴのみに絞った内容で、個人あるいは複数人数の立場から成る「私はこう考える」的な見方や推理は提示されていない。
下山事件研究会(以下、【研究会】と略)というのは、下山事件の時効が成立した昭和39年の夏に各界の識者が自主的に結成したグループで、その代表は(事件発生当時)東大の総長であった南原繁。【研究会】のメンバーは10人ほどいるが、南原以外では『日本の黒い霧』の作者でありGHQの謀略を主張した松本清張、そして【研究会】事務局を担当していたが後に退会、『下山事件全研究』を上梓して〈自殺説〉派の筆頭となっていった佐藤一、とりあえずこの二名さえ押さえておけばいいと思う。(本書の中で事務局=佐藤一であるクレジットは無い)
『資料・下山事件』の編集方針は〈自殺説〉〈他殺説〉そのどちらにも偏重しないよう、イーブンに推理や判断に必要なデータのみ提供するのを第一義としているものの、松本清張の存在しかり、また下山総裁の屍体を司法解剖した古畑種基教授と桑島直樹講師は当時南原がトップとして君臨していた東大の所属だった人達ゆえ、ついつい読み手が〈他殺説〉の方へ傾きがちな事情を孕んでいるのは注意しておいたほうがいいかもしれない。
あ、そうだ。前回の記事でも触れたけど清張が『日本の黒い霧』の中でこだわっていた日暮里駅で発見されたという「5.19下山缶」の落書きについては、本書では一切ノータッチ。つまり誰も事件の証拠として重要視してはいなかったみたい。ジャンジャン。
♣ 注目すべきは【研究会】メンバーによる事件に関わった人々からの聴き取り。
証言協力者は古畑種基/桑島直樹/平正一(当時の毎日新聞記者、『生体れき断』著者)/
関口由三(当時の特別捜査本部捜査主任)/
矢田喜美雄(当時の朝日新聞記者、『謀殺・下山事件』著者)/
塚元久雄(当時の東大裁判化学教室助教授)/加賀山之雄(当時の国鉄副総裁)/
下山常夫(下山総裁実弟)/宮下勝義(当時、米軍情報部員として活動)。
彼らの証言のうち他の文献へ部分的に引用されているものもあるけれど、それぞれの口から語られる肉声はリアルさを伴っており面白い。本書には古畑/桑島両氏の見解に噛付いた〈自殺説〉派の意見も勿論載っていて、新日本医師協会と中舘久平(慶応大学教授)の言がそれだったりするのだが、この人達の言い方がやけに感情的なのはあまり感心しない。
世間では〈他殺説〉を信じる人のほうが圧倒的に多かったから熱くなる気持ちは解らんでもないけれど、人の名前をイニシャル表記でごまかしつつ食って掛かるような物言いをしたんじゃ、(喩えが悪くて恐縮だが)自民党のする事なら箸が転んでも難癖付けて批判さえしておけばいいとでも思い込んでいる野党みたいで、これでは他者を納得させにくいし自ら損している。同じ〈自殺説〉派でも平正一のように、他人の揚げ足取りではなく淡々と見解を述べるほうが読み手は受け入れやすい。中舘教授は残念ながら遺体や遺留品を直接見ていないのも弱みかな。
下山家唯一のスポークスマンだった下山常夫が「自殺だとは、とても考えられない」とハッキリ言い切っているのを読めるのは本書ならでは。それに比べて、宮下勝義は戦前特務部にいて戦争犯罪人扱いだったところを米軍側から力を貸してほしいと云われて情報部員になったというが、貝谷なる人物が事件当日、総裁と三越で会う約束をしていたなんて語っているけど、ホントか?この種の話はどうも疑わしくて。
♣ 読みどころは他にも。いわゆる〔白書〕と呼ばれる「下山国鉄総裁事件捜査報告」。
例えば三越付近及び五反野付近といった重要ポイントにおける警察サイドの聞き込み情報が時間軸に沿って細かく一覧表にされているんだけど、私は総裁が姿を消した日本橋三越付近よりも、屍体の発見された五反野付近での目撃情報のほうに断然重きを置いている。
推理の手掛かりのひとつが、総裁の使っていたメガネ。
他殺であれ自殺であれ、実際メガネは轢断現場から発見されていない。
(野良犬がどこか遠くへメガネを咥えていってしまった? そんなもん、咥えていくか?)
下山氏はかなり視力が悪くて、メガネをしていないと、どうしようもない程だったという。
本書に収録されている下田光造の論文のとおり、仮に総裁が初老期欝憂症だったとしよう。
第三者の関与なんて無く、完全な〝自己彷徨〟の果てに常磐線のレールの上へ自分の首と両足首を切断してくれとでもいわんばかりに、(レールに対し)キレイな垂直状態となって横たわるには、死亡推定時刻だと既に辺りはもう真っ暗になっている筈だし、もし総裁が死ぬ前にメガネをどこかで落っことしていたのなら、どうやって土手の上の線路まで首尾よく辿り着いたというのだろう?〈自殺説〉を信じようとすれば結局いつもそういう点が引っかかってしまう訳よ。
♣ 轢断されるよりも前の時間帯、つまり7月5日の夕刻以降、道端や常磐線路上や畑の中を下山総裁らしき人物が一人でウロウロしている様子が何人もの地元の人に目撃されている。裕福な紳士が住んだり通りかかることもない、寂しい場末の土地だった現場付近において、背広を着てガタイのいい上品な男性を見かけたら相当目立つので見間違えようもないし、警察がなにかの意図をもって地元住民にありもしない嘘を証言させるといった、探偵小説でもありえんようなスペクタクルな暗躍でもしていない限り、五反野付近で総裁本人もしくはそれらしき替玉の男がうろついていたのは動かし難い事実。
全くの誤認も含め、様々な目撃談が時系列に表記してあるけれど、
人間というものは服や靴の色なんて、それほど正確には覚えていられないと私は思う。
ただ、彼らが目撃したのが上品そうな恰幅のいい中年男性であったこと、
(そしてココが一番重要なのだが)その人物がメガネをかけていたかどうか、
この二点に限っては見間違えたり誤って記憶する可能性はかなり少ないんじゃなかろうか。
五反野付近での目撃談の殆どは総裁らしき人物が末広旅館を立ち去った後のもので、7月5日という夏の夜7時前後の現場周辺はまだ明るかったのか、あるいは暗くなっていたのか、それも微妙。「遠くから見かけたので顔は正面からちゃんと見えなかった」とか、「よく見てなくて覚えてもいない」っていうのならOKだけど、「その人はメガネをかけていなかった」なんて証言が混在しているのが困るンだよな。初老期欝憂症でモーローとして自殺する直前の総裁はメガネをかけたりはずしたりしていたのか(替玉ならそんな小細工をする必要は無いのだ)、 疑問は深まるばかり。
メガネの話からつい長くなってしまったけれど、〔白書〕を読んでいて事件現場近くをうろついていた男が本人だったのか替玉だったのか言及されている箇所は特に熟読してしまうのだった。
♣ その他、「新聞報道からみた下山事件」では事件発生から一ヶ月にわたる『朝日』『毎日』『読売』の報道内容を集成。昭和24年「衆議院法務委員会議録」では参考人として召喚された中舘/古畑、そして小宮喬介名古屋大学教授(〈自殺説〉派)/田中栄一警視総監/坂本智元刑事部長の肉声が読めるが、発言の土俵が公(おおやけ)過ぎるのもあってか、国会答弁そのまんまな感じがして、読んでてもどかしさも感じた。
本書制作時に判明していた下山事件参考文献の一覧もあったり、総合的には満足。
本書は活字中心の資料アーカイヴだが、できることなら当時の写真をガッツリ網羅した下山事件のヴィジュアル・アーカイヴ本が欲しいな、と思う。これだけの大事件だし、あの頃撮影された写真はかなりの数になると想像されるものの、いろいろ権利問題がうるさくなって今ではそんなものを刊行するのはムリなんだろうか。資料的意義があってマネーにもなると思うんだが。
(銀) 私個人の話をすると、五反野方面には友人知人もなく、足を運ぶ機会はまず無かった。下山事件の時代にはまだ影も形もなかった首都高を車で走りつつ小菅JCTを通り過ぎるくらい。たった一度だけど90年代の終わり頃、受付の派遣で私の仕事場へ来ていた女性のアパートに一晩泊めてもらう機会があり、その人の住まいがあのあたりだった。
彼女は明るい性格で実家は藤沢のほうだと云う。特に勤務先が東京の東側でもないのに、なんであの辺に住んだのか少し不思議だったけれど、その理由を問うた記憶もない。ただあのあたりは下町とはいえ、なんとなく物寂しい雰囲気がしたのは確かに覚えている。昔と今とでは東京も大きく変貌したけれど、小菅刑務所は今でも東京拘置所として同じ場所に立地しているし、若いOLが一人で住むには適していないのでは、とも思った。でもそれは自分があの辺のことをよく知らないからそんな印象を受けたのかもしれない。彼女は元気にしているかな?