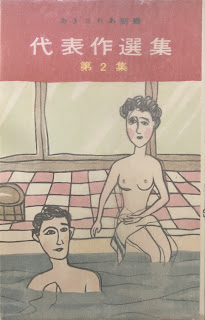『怪樹の腕~〈ウィアード・テールズ〉戦前邦訳傑作選』(☜)が世に出て早や十二年が過ぎたのか・・・・それだけ長い年月を掛けたからこそ今回の企画も素晴らしい内容に仕上がっているのはわかっちゃいるけど、もう少し会津信吾にはハイペースで本を作ってほしいなあ。今や何の考えも無しに垂れ流される、このジャンルの新刊。作り手の知性とセンスを感じる書物なんて、どこを探しても無い。
❁「疾病の脅威」高田義一郎(『探偵趣味』昭和3年1月号発表)
❁「屍蠟荘奇談」椎名頼己(初出不明/底本は昭和3年刊『屍蠟荘奇談』赤木書房)
❁「亡命せる異人幽霊」渡邉洲蔵(『蜂雀』昭和4年1月号発表)
❁「火星の人間」西田鷹止(『冨士』昭和4年10月号発表)
❁「肉」角田喜久雄(『文学時代』昭和4年10月号発表)
❁「青銅の燭台」十菱愛彦(『グロテスク』昭和4年12月号発表)
❁「紅棒で描いた殺人画」庄野義信(『犯罪科学』昭和5年10月号発表)
❁「鱶」夢川佐市(『怪奇クラブ』昭和5年11月号発表)
❁「殺人と遊戯と」小川好子(『犯罪科学』昭和6年3月号発表)
❁「硝子箱の眼」妹尾アキ夫(『文学時代』昭和6年6月号発表)
❁「墓地下の研究所」宮里良保(『若草』昭和6年8月号発表)
❁「蛇」喜多槐三(『犯罪実話』昭和7年1月号発表)
❁「毒ガスと恋人の眼」那珂良二(『経済往来』昭和7年3月号発表)
❁「バビロンの吸血鬼」高垣眸(『少年世界』昭和8年1月号発表)
❁「食人植物サラセニア」城田シュレーダー(『犯罪実話』昭和8年2月号発表)
❁「首切術の娘」阿部徳蔵(『犯罪公論』昭和8年5月号発表)
❁「恐怖鬼侫魔倶楽部奇譚」米村正一(『犯罪公論』昭和8年6月号発表)
❁「インデヤンの手」小山甲三(『週刊朝日』昭和10年5月1日臨時増刊号発表)
❁「早すぎた埋葬」横瀬夜雨(『奥の奥』昭和11年9月号発表)
❁「死亡放送」岩佐東一郎(初出不明/底本は昭和14年刊『茶煙亭燈逸伝』書物展望社)
❁「人の居ないエレヴェーター」竹村猛児
(初出不明/底本は昭和14年刊『物言はぬ聴診器』大隣社)
いつも学ぶべきところが多い会津の仕事。今回も各短篇の初出をチェックし『蜂雀』という雑誌の存在を初めて知った。ネット検索してみたものの殆どヒットせず、どんな感じの表紙なのか、それすら想像できん。あと、いかにも小説が載ってなさそうな誌名の『経済往来』は古書店で手に取って中身をチェックした記憶が無い。ここまであらゆる古雑誌を調べ倒しているがゆえの〝目利き〟なのだろう。耳慣れない作家と作品が多数並んでいるのは、作品の取捨選択に際し『新青年』掲載作が一切オミットされているのも大きな理由のひとつ。
『若草』は『文学時代』『冨士』『週刊朝日』と異なり、私のBlogとは縁遠そうな文芸誌だと思っていた。じっくり探せば「墓地下の研究所」みたいにヘンなのが紛れているのかも。そして『グロテスク』『犯罪科学』『犯罪公論』『犯罪実話』なんか探偵趣味と一見親和性がありそうなのに、評価を得て後世に残った小説が見当たらず、どちらかといえばイカモノ記事や実話で売ってた印象。でも上手く短編小説が拾い出されアンソロジーの一部になっていると、それなりのアイデンティティーも見えてくる。
歴史に淘汰されてしまった無名作家の作品を古雑誌の中に見つけて単体で読んでも、正直面白く感じられないことの方が多い。ところがこうやって一つのテーマを設け、似たベクトルの短篇をズラリ並べてみると、単体では発し得なかった輝きを放つようになるから不思議。フツーの読者に「気持ちワル~イ」と敬遠されそうなものばかり目立つ訳ではなく、小山甲三「インデヤンの手」は人種の壁に捉われない温かみがあったり、全体を通して単調じゃないのもGood。唯一ジュヴナイルだからか、本書のうち最も弱い高垣眸「バビロンの吸血鬼」が表題作になってて、つい笑ってしまうが、これの雑誌掲載時に挿絵提供していたのが岩田専太郎(325頁を見よ)。力の入った挿絵を描いてもらえてメジャーな作家は得だねえ。
河出文庫『盗まれた脳髄 帆村荘六のトンデモ大推理』に見られる(こちらの記事を参照/☜)頭の悪いポリティカル・コレクトネスでもって製作されたトンデモ本を嘲笑うかのように、発表当時の表現を規制も改悪もせず正しく復元している本書。東京創元社と会津信吾はごく当り前の本作りを行っているだけだ。河出書房新社と新保博久はなぜ実写版の映画「白雪姫」が世界中で大不評なのか、よ~く考えるこってすな。
(銀) 本書における会津信吾・名言集。
〝戦前が暗黒時代だと思っているのは、教科書しか読んだことのないやつか、その教科書を書いたやつのどちらかだ。そんな奴らは放っておけ。〟
〝ある意味、ホラー小説の消長は平和のバロメーターだと言える。〟
〝『少年倶楽部』のモットーが「おもしろくてためになる」ならば、こちら(註:『少年世界』のこと)は「おもしろいけど、ためにはならない」で行こうとでも考えたのだろうか。〟