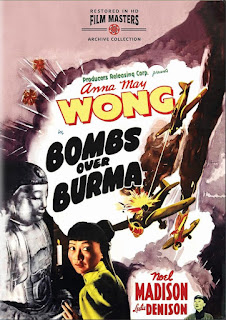往年の著書『地獄の映画館』の中で小林信彦が述べている二つの点に着目。
〝本格物のトリックってやつは、
画面でタネ明かしされると、なんだかバカにされたような気持ちになるのだ。〟
〝SF映画は、史的にみても、ずっと、マイナーな存在であった。
一九五〇年代に作られたSF映画の多くは、ゲテモノ、特撮を用いた見世物映画であった。
(中略)
後年、SF映画史を語るとすれば、おそらく「2001年(宇宙の旅)」以前、以後、といった区分がなされると思う。SF映画がプログラム・ピクチャーでなくなり、つまり〈芸術〉の殿堂に入ったという意味合いで。〟
小林の言うとおり、「2001年宇宙の旅」(1968年公開:監督 スタンリー・キューブリック)がエポックメイキングな作品になったことで、SF映画はB級/ゲテモノ扱いのレベルとは段違いの大作が生み出されるようになった。しかし、当Blogで取り上げている類の小説を原作に持つミステリ映画となると、〈芸術〉の殿堂に入るどころか、映画の専門家たちが選ぶ古今東西傑作映画セレクションの中にランクインするかどうかも怪しい。その種の映画は果たしてどれぐらい評価されているのだろう?
本来ならせめて十名ぐらいのクリティックスが選ぶそれぞれのベスト100作品をチェックすべきところだけど、それはさすがに大変だし、なにより小林は映画同様、ミステリにも精通している人だから、本書『2001年映画の旅/ぼくが選んだ20世紀洋画・邦画ベスト200』における洋画ベスト100+邦画ベスト100を参考にさせてもらって、原作のあるミステリ映画に小林が推したくなるようなものは何本あるのか、調べてみたいと思う。
●
個人の嗜好とはいえ、小林がそれぞれベスト100を選ぶ際に課したルールのうち、次の点は明記しておかなければならない。
・ 小林自身が繰り返し観た作品、または、もう一度観たいと思っている作品
・ アニメーション映画は除外
こうしてまず20世紀の洋画100本が選ばれた訳だが、そのうち探偵小説/推理小説を一応原作に持つ作品では次のものがラインナップに上がっている。
「影なき男」(1934年公開:原作 ダシール・ハメット)
「バルカン超特急」(1938年公開:原作 エセル・リナ・ホワイト)
「裏窓」(1954年公開:原作 コーネル・ウールリッチ)
「必死の逃亡者」(1955年公開:原作 ジョセフ・ヘイズ)
「現金に体を張れ」(1956年公開:原作 ライオネル・ホワイト)
「情婦」(1957年公開:原作 アガサ・クリスティー)
「めまい」(1958年公開:原作 ボワロー=ナルスジャック)
「サイコ」(1960年公開:原作 ロバート・ブロック)
「太陽がいっぱい」(1960年公開:原作 パトリシア・ハイスミス)
「血とバラ」(1961年公開:原作 J・シェリダン・レ・ファニュ)
「羊たちの沈黙」(1991年公開:原作 トマス・ハリス)
私の好みの海外ミステリ作家はあまり含まれていない。
●
よくフィルム・ノワールってどこまでを範疇とするのか、議論になる。ミステリ映画もその対象をどこまで広げるのか明確なラインは無い。ともかくさすがは小林信彦、100本中これだけ原作小説のある作品をセレクトしており、これにいわゆる準ミステリ、つまり、ミステリ作家の原作こそないもののサスペンス/スリラー/フィルム・ノワール/クライム・ストーリーに該当する映画を加えると「ミュンヘンの夜行列車」(1940年公開)をはじめ更に数が増えるが、そんなに列記したら煩雑になるので、あとは本書で確認して頂きたい。
さて、次は邦画ベスト100。探偵趣味を内包する作品のなんと少ないことよ。強いて言えば、「待って居た男」(1942年公開)は上記「影なき男」シリーズの換骨奪胎だそうだし、黒澤明の「野良犬」(1949年公開)もフィルム・ノワールと呼んで差し支えないだろう。が、悲しいかな私のBlogに登場する日本探偵作家の小説を原作にしたものは影も形もない。
「赤い殺意」(1964年公開:原作 藤原審爾)、「霧の旗」(1977年公開:原作 松本清張)はランクインしているが、この辺の作家にミステリ的な愉しみを求めていないので今日のところはスルー。
以上の結果を見て解るとおり、極論と云われようとも、昔のショービズ界には論理的な本格探偵小説を正しく映像化する意識と技術が著しく欠落していて、ミステリ映画といってもその殆どがハードボイルドやスリラーでしかない。
ただ、SFものに差を付けられているとはいえ論理性を持たせたミステリ映画も「オリエント急行殺人事件」(1974年公開:監督シドニー・ルメット)あたりから、それなりに大きな興行収益を得るようになったのではないか。それ以前は『地獄の映画館』にて触れられているディクスン・カーの「火刑法廷」を映画化した「火刑の部屋」(1963年公開:監督ジュリアン・デュヴィヴィエ)など、原作の良さがまるで活かされていないものばかり。
本格以外にも、ルーファス・キング作「青髭の女」を映画化した「Secret Beyond The Door」だって監督フリッツ・ラングと聞けば期待してしまうけれど、これまたイマイチな出来。
日本の映画界はもっと酷い。謎解き要素のある探偵小説を原作にしたもので、どうにか観られるようになったミステリ映画と言えば、例の「犬神家の一族」(1976年公開)より前になんかあったっけ?結論。探偵小説は活字で楽しむのが一番。
(銀) 小林信彦の洋画ベスト100といえば、あれだけ『文春』の連載で褒めたたえていたニコール・キッドマン出演作がひとつも無いが、よく考えたら彼女がビッグになっていくのはトム・クルーズと離婚したあと。もしこのベスト100セレクトが十年遅かったら、何かしらランクインしてたかな?
■
小林信彦 関連記事 ■