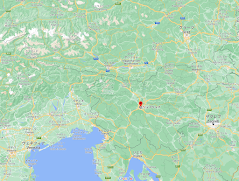▦ 『ミステリーの料理事典』及び、その改題増補版『殺人は面白い 僕のミステリ・マップ』を再構成+αしたもの。ただし元本にあって今回割愛されている部分もあるので、上記二冊に愛着があるならお持ちの方はそのまま持っていてもいいかもしれない。
《 Ⅰ 》
第一章
ぼくとミステリ
― 大いなる誤訳人生
以下、第三章までは著者へのロング・インタビュー。田村は昭和28年に早川書房に入社し翻訳者として働いた。江戸川乱歩/植草甚一についてはこの章だけでなく他でも適宜触れられている。
「別に探偵小説の評論家になろうとも、作家になろうとも思ったわけではないんです。」
「わざと誤訳してもいいと思う。時と場合によっては。(中略)戦前、延原謙という翻訳家は、日本人に発音しにくい固有名詞を、発音しやすい名前に変えてしまったといいます。」
「最後に活字で読むもので残るのは、探偵小説と詩なんです。」
第二章
ミステリは特別料理
― 味、知恵、ユーモア
「人殺しの話を楽しみながら読むというのは、ユーモア以外の何ものでもないでしょう。」
「ユーモアというのは〝視点を変える〟ってことなんです。」
「ただ殺人が書かれているからといって探偵小説だということにはならない。その意味で、『罪と罰』だって、探偵小説とは呼べない。あれは、政治小説・宗教小説でしょう。」
第三章
ぼくの好きな料理
― これがグルメの条件です
ポオからロス・マクドナルドまで、四十組ほどの基本的な海外ミステリ作家を紹介。初心者にも手軽に楽しめる案内になっている。
《 Ⅱ 》
クロフツ/クリスティ/シムノン/クイーン、彼らの作品のために執筆した解説とエッセイ。
《 Ⅲ 》
乱歩と植草を回想するエッセイ。そして生島治郎/都筑道夫との個別対談。『E・Q・M・M』(エラリー・クイーンズ・ミステリ・マガジン)に関する情報を知りたければこちらをどーぞ。
田 村「吉本隆明ファンばっかりいるような世界では探偵小説は生まれないわけだ。」
生 島「三島由紀夫も非常に臆病な死に方だからね、あれも。」
田 村「あれは戦争に行ってないからね。自分が死ぬんだったら、
自分一人でこっそり死ぬんだな。死にたかったらだまって死ねばいいんだよ。」
都 筑「『EQMM』をやってくれないかといわれたとき、ぼくは乱歩さんにたのまれて、
新潮社のために作品のセレクトをしかけていたんです。」
田 村「創元社につづいて、新潮社でも翻訳ミステリを出していたね、あの当時。」
都 筑「たしか探偵文庫といいましたよ。」
▦ 巻末には【資料編】と題したボーナス・トラック。
(銀) 本書の中で田村隆一が「で、その当時のミステリファンというのは、やはり病的なのが多いのよ。今と違ってね。ある意味じゃ、ちょっと隠微なの。戦後ずいぶん変わってきたけどね。」と語っているくだりがある。平成後半以降、喜国雅彦の本に登場する類いの、ミステリ本を金の種かなにかと勘違いしたクズ野郎が増え、内容もよく知らないのにレアである事ばかりを矢鱈ありがたがる病気に脳を侵されてしまった一部のミステリ中高年どもの実態のほうが、田村の時代よりもはるかに病的であるのは私のBlogで度々お伝えしているとおりでございます。